『蝶の舌』、『メキシカン・スーツケース』、『アイ、カルメーラ!』と今まで、スペインの内戦を共和党側の立場で接して来たことが多かった中、ファランへ党のサンチェス・マサスの銃殺事件を通してのエピソードから、この作品を通して、反対側にもあった物語や思いを知ることができました。
"Soldados de Salamina" Javier Cercas ( 宇野和美 訳)
又、スペイン語の友人Kさんからのお薦めで読んだ作品だ。
彼女は本当にいつも素晴らしい作品を紹介して下さる。
スペインの内戦の終わりの頃クリェイという町で共和国軍による集団銃殺事件がありました。それはちょうどスペインの大詩人、アントニオ・マチャードの死と同じ頃の出来事でした。
その時、2名が銃撃を逃れて森へ逃げこみました。そのうちの一人がファランへ党の中心人物で詩人のサンチェス・マサス、彼は森の中で若い兵士に見つかるのですが、兵士は彼を数秒間じっと見つめて、仲間からの「いたか?」とかけられた問いに、「こっちにはいない」と答えてきびすを返して去って行ったのです。
というエピソードがあるのですが、それをもとに、この兵士は何故彼を助けたのか?彼は一体誰だったのか?という問いを追いながら作家であり新聞記者であるハビエル・セルカスが取材を重ねていく話です。
人生の岐路にいたハビエルが最後に辿り着く境地がなかなか良かったです。
最後に辿り着いた人物は、もう老人で、戦争でまだ何も素敵なことを体験もせずにただ死んで行ってしまった仲間の若い兵士たちを思わない日はないと言うのですが、彼が思い出さなかったらもう誰も彼らのことを知らないのだから・・・と。
国を守る為に死んで行ったのに、誰も思い出してあげることすらできない。
作者は書くことで、たとえその人が死んでしまっても、誰かの心の中に残せると思うのだろう。
こんな一節がある:
「なぜなら、こたえのないことが唯一のこたえだと、もうわかっているから。唯一のこたえは、ひそやかな、はかりしれない喜びなのだ。残酷さと隣あわせのもの、理性とは違うが本能でもない何かだ。血液がいつでもその血管の中を流れ、地球が変わらぬ軌道をたどり、どんな生き物もつねにその生き物でありづづけるのと同じ盲目的な頑迷さで、理性の中に生きつづけている何か。小川の水が石をよけて流れるように、言葉を避けていく何か。なぜなら言葉とは、自分をあらわすため、自分が言いうることをあらわすためにつくられたものだから。」
何故か『黄色い雨』をちょっと思い出した。
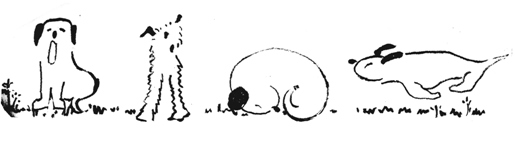

0 件のコメント:
コメントを投稿