久しぶりに長編小説を読んだ。
ベルナルド・アチャガの「アコーディオン弾きの息子」という作品だ。どうして読みたいと思ったかというとバスクの作品だったことと、訳者がバスク語から直接訳したという情報に惹かれたためだった。
とても小さな文字で573ページもあったが先が読みたくてたまらず一気に読んでしまった。
アチャガはスペイン語とバスク語でこの作品を書いたらしいので、翻訳のギャップは誰かが訳したスペイン語から日本語にするよりもはるかに軽減されるのでちょっとワクワクした。
以前読んだ『サラミスの兵士たち』がとても良かったので同時代の骨太の作品を読んでみたかったのだ。
カリフォルニアで亡くなったバスク出身のダビという「アコーディオン弾きの息子」の生涯が描かれているのだが、それを書いたのはのちに作家になった親友のヨシェバだ。彼はダビが残したバスク語で書かれた回想録と自分の記憶をもとにその作品を書いた。
そのせいで章によっては『僕』がダビなのかヨシェバなのかこんがらがって奇妙な錯覚に陥って困ったが、読み返すとこれはダビだとほとんどがダビであるとみてよいだろう。
私の印象ではダビの母方の伯父フアンと故郷の親友ルビスがとても魅力ある人物で描かれている。根本では彼らがダビの生涯に大きな影響を与えているのだが、ダビは生涯ずっと秘めて持ち続けていた一つの疑問を心の奥底で気にかけながらも、むしろ時代やまわりの人々に流され、受動的に生きてきた気がする。
初めて自分の意思で行動したその後もやはり流されて生き続けたような気がする。流されて過酷な人生を生きてきてもずっと持ち続けたダビの子供っぽいまでの素直さのようなダビらしさは私の心に残った。
流されるということ、それが決して悪いことという意味ではなく、彼が自分の意思で何を選択したとしても免れることのできない不条理な時代だったのだと思う。
大作過ぎて内容の説明をしきれないのと、自分の理解がまだ追いついていないので多くを語れないが、言葉と記憶と故郷と暴力と時代と命、そして蝶々が私の読み取ったキイワードだ。
あまりにも多くのことが込められた作品なのでなかなか整理できない。今回は自分の記憶のためにメモとして書き記すだけで、もう一度読み直して又改めてまとめようと思う。
いたるところで存在を感じる蝶の姿が私の脳裏をかすめる。
蝶は本当にひらひら不思議な動きをし、生命の再生を感じさせる。私の庭にも最近失ったものの命を感じるメッセンジャーのような蝶がしばしば出現し、気ままな動きをしながら私に語りかけてくる。
そしていつの間にか蝶と話している自分がいる。
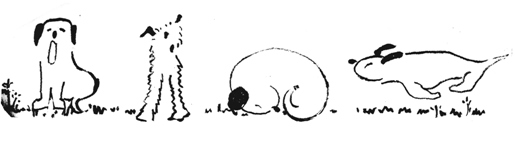

0 件のコメント:
コメントを投稿