なかなか手強いオババ。
鏡の前で:
自分で買った洋服なのに、「よくまあ、こんな野暮ったい洋服買ったもんだわね!いつ買ったのかしら?」 90歳のバアさんがつぶやいている。
アイボリーの地に熱帯魚があちこち泳いでいる。いかにも当時のオババが好きそうな結構面白い図柄だ。
私から見ると、今のあなたのセンスの方が余程危ないんですが・・・
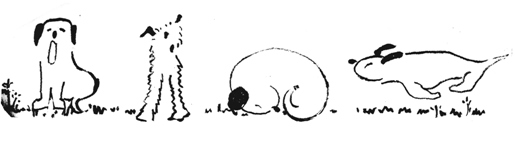
2012年5月31日木曜日
アリ、アリ・・・またアリにやられた〜!
息子と携帯で話しをしながらふとバルコニーを見ると、アリが行列を作っている。下から上へとせっせと歩いているではないか。いやあ〜〜な予感がした。
クロアリの大名行列だ!(下にぃ〜下にぃ〜、ではなく、上にぃ〜向かっているが)
よく見ると柱の根元が縦に15cm程モコモコとオガクズ状のもので盛り上がっている。アリの行き先に眼を移すと、二階のバルコニーの接合部分の裏側がぁー!!!何とこの写真の状態に!!
「去年修理をしたばかりなのにぃ!」と息子に向かって半べそで文句を言った。
このブログを始めたばかりの頃だったので、見てみると去年ではない、一昨年の8月だ。やはり老化現象は始まっている。暑い熱い夏に見つけた同じようなシーン・・・クロアリに巣作りされて空洞になったバルコニーの柱や手すりなどをを替えてもらいかなりな範囲で修理をした。その後虫が異常発生しているから、と住宅の方のシロアリの防蟻処理までしてもらった。支出大!
このオガクズには、良い思い出はなく、白樺が鉄砲虫にやられた時も思い出す。
春先にオガクズが白樺の根元に散撒かれていた。悪夢!!植木屋さんにきていただき消毒してもらったので、どうにか白樺は生き延びた。その年はすごい数の白樺がやられたらしかった。
それから毎年春になるとビクビクしながら「オガクズは〜?」とチェックしている。
白樺はチェックしていたのに、バルコニーは修理したばかりだったからと、チェックを怠っていた。深く反省・・・
虫は、何でも食べてしまうから厄介だ。
折角植えたルッコラもパセリも夜盗虫が一晩で食べてしまう。パセリなど頭が一つも残っていないから、無惨だ! 昼間、土を掘り起こして眠っている緑色の虫を箸でつっついてやっつけないではいられない。鬼平犯科帳!
柱も家も食べられてしまうかもしれないから、「朝起きたら家がなくなっていた!」なんてことにならぬよう、油断せずにチェックを怠らずに日々監視体制に入ろう。
2012年5月30日水曜日
なかなかいいぞ! X3 (xdrive 20i)
さて、やってきたミネラルシルバーの四駆の新車X3は、昨日は時間がなく乗れなかったので、今日はオババの所へ早速行って来ました。
何しろ私には巨大に感じ、幅があるので、お借りしていた車が小さかった関係上感覚がずれるのでは?と恐かったのですが、ホームまでの細い道もそれほど気にならず、、、多分今までの530iと高さ以外のサイズが似ていたのでしょう、全然問題なく、快適でした。
私は、前の車の乗り心地が大好きで、ステアリングとアクセルのパワフルな連動感と信頼性の高いブレーキが身体に馴染んでいて、あの地面に吸い付くような感じがたまらなかったのですが、それと比べると車がごつい割に、結構全体が軽く感じ、軽やかで気分爽快!でした。
これはこれで、なかなか良かったです。
一日目ですっかり馴染んでしまいました。
まず、とても運転しやすいこと。
つまり車高が以前と比べるとかなり高いので(むしろ二台目のvolvoに近い?)、今までの地面に沈み込んだような感じから這い上がり、上から余裕で見下ろすバスの運転手さんのような気分で運転できるので、スポーツカーをぶっ飛ばす気分にはならず、むしろ慎重な安全運転ができるかな?と言う感じでした。
早く軽井沢へ行って運転したいです。
そして、新車は新車、つまり12年の歳月は車の進歩にはやはりそれなりの意味がある、ということでしょうか?
以前の重厚感も大好きですが、やはりメリットがたくさんありました。
私はマニュアル、アナログ人間なので、自分の眼で見て、肌で感じる、つまりバックして車庫入れするにしても、やはり窓から顔を出して、肌で感じたい人なのですが、やはり後ろの障害物や距離がスクリーンでわかるのは、ダブルチェックできて悪くないなと思いました。
ミラーにしても角度などうまく計算されていてとてもよく見えますし、設備も良いです。
折角の12年分です、便利さは、それなりに利用しましょう!
ということで、安全運転で、 ¡vamos!
私はこうでしたが、果たしてKzさんは? 難しい変人だから
何しろ私には巨大に感じ、幅があるので、お借りしていた車が小さかった関係上感覚がずれるのでは?と恐かったのですが、ホームまでの細い道もそれほど気にならず、、、多分今までの530iと高さ以外のサイズが似ていたのでしょう、全然問題なく、快適でした。
私は、前の車の乗り心地が大好きで、ステアリングとアクセルのパワフルな連動感と信頼性の高いブレーキが身体に馴染んでいて、あの地面に吸い付くような感じがたまらなかったのですが、それと比べると車がごつい割に、結構全体が軽く感じ、軽やかで気分爽快!でした。
これはこれで、なかなか良かったです。
一日目ですっかり馴染んでしまいました。
まず、とても運転しやすいこと。
つまり車高が以前と比べるとかなり高いので(むしろ二台目のvolvoに近い?)、今までの地面に沈み込んだような感じから這い上がり、上から余裕で見下ろすバスの運転手さんのような気分で運転できるので、スポーツカーをぶっ飛ばす気分にはならず、むしろ慎重な安全運転ができるかな?と言う感じでした。
早く軽井沢へ行って運転したいです。
そして、新車は新車、つまり12年の歳月は車の進歩にはやはりそれなりの意味がある、ということでしょうか?
以前の重厚感も大好きですが、やはりメリットがたくさんありました。
私はマニュアル、アナログ人間なので、自分の眼で見て、肌で感じる、つまりバックして車庫入れするにしても、やはり窓から顔を出して、肌で感じたい人なのですが、やはり後ろの障害物や距離がスクリーンでわかるのは、ダブルチェックできて悪くないなと思いました。
ミラーにしても角度などうまく計算されていてとてもよく見えますし、設備も良いです。
折角の12年分です、便利さは、それなりに利用しましょう!
ということで、安全運転で、 ¡vamos!
私はこうでしたが、果たしてKzさんは? 難しい変人だから
2012年5月29日火曜日
よい歳になるかも・・・
昨日は、私の61歳の誕生日だった。
いつもの年の如く、何も期待していなかったのだが、この日は偶然にも待ちに待った車の到着日。新車はBMW X3 (xDrive20i) 丁度モデルが変わったばかりで、日本上陸第一号の荷でやって来た。とても急いでいただいたので、多分私が日本で20iに乗る最初の所有者かもしれない。
前のブログの如く、12年乗った愛車に別れを告げ、しかし車検を通らなかったため乗れる車がない状態。お借りした車で過ごした1ヶ月以上は、私の性格上、人のものを傷つけたら申しわけない・・・と安心して使えず、緊急以外に使わなかった。
やっと気楽に乗れるぞ!
納車は夕方の6時、その前にスペイン語の授業だった。
Kzさんは仕事で沖縄。
教室に入ると、スクリーンに "Feliz Cumpleaños" (Happy Birthdayの意)と大きな文字で映し出されている。
前のクラスの誰かの誕生日だったに違いない・・・自分をお祝いしてもらっているみたいないい気分。
パトリシア先生に「誰か誕生日だったのですか?」とお聞きすると
「セニョール・タカハシが80歳の誕生日だったのよ、あのお元気さで80歳!」
(タカハシさんはとても素敵な紳士、冬のクラスでご一緒したけれど温かくて控えめでいつも笑顔の絶えない本当に素敵なおじさまなのだ。)
「わあ、すごい、そうだったのですね。 ところで今日、私も誕生日なのです」とつい言ってしまったら、先生眼を輝かせて・・・
「でも、私は80歳じゃありませんから」と言うと、ニッコリして、
「No, Señora Sora」素敵な笑顔。
「un momentito (ちょっと待ってください)」と教室を出て行かれた。
メキシコの誕生日のお祝いのときの歌をプリントしてもらいに行ってくださったのだ。
授業の途中で、すごい嵐になり、雷に雹に強風に・・・みんなで窓を開けて眺めてしまった。教室内で良かった!
雨女の私も最近雨に遭わない。雨でも嵐でも、危機一髪!家に入った瞬間に始まるから、少し運が向いて来たのかもしれない。(今までは、外に出れば快晴でも雨が降ってきたものだ)
まるで悪夢のようだったここ数年の厄払いみたいに、スッキリ!デビルの灰を洗い流されたような気がする。
最後には "Las Mañanitas" という、メキシコの誕生日に歌う伝統的な歌をクラスのみんなと一緒に歌って下さった。平和な明るい曲。先生の声はとてもきれい。
みんなの声は温かい・・・こうして、幸せな61歳がスタートした。
帰宅後、偶然急いで買うことになった初対面の我が車はとても素敵で、仲良くなれそうだった。何しろまだパンフレットもできてないのだから。どんな車がやって来るのかドキドキだった。
営業担当のMさんは、「誕生日の納車って、ほとんどないのですよ。とても珍しいのです」と芍薬とバラとトルコ桔梗のとても私的色合いの素敵な花束を下さった。
女性にはいつも花束は幸せを運んでくれる。私はとても幸せで芍薬のようはポッペになったのではないだろうか?
思いがけないことばかりの上、自分がレディになった気分で、素敵な誕生日だった。(そういえば去年はガツガツ食べてお腹を壊して、上に下に一晩中苦しんだのだった。嫌なものを全部出してしまった意味合いにおいては、ゼロからのスタートだったが、今年はスタート時点で二年前より上向きだ)
さあ、車は4WDのターボ、山道用だ。
おてんばな私はさりげなく、格好良い中年になれるように
"ぶっ飛ばして、行ってみよう!!"
いつもの年の如く、何も期待していなかったのだが、この日は偶然にも待ちに待った車の到着日。新車はBMW X3 (xDrive20i) 丁度モデルが変わったばかりで、日本上陸第一号の荷でやって来た。とても急いでいただいたので、多分私が日本で20iに乗る最初の所有者かもしれない。
前のブログの如く、12年乗った愛車に別れを告げ、しかし車検を通らなかったため乗れる車がない状態。お借りした車で過ごした1ヶ月以上は、私の性格上、人のものを傷つけたら申しわけない・・・と安心して使えず、緊急以外に使わなかった。
やっと気楽に乗れるぞ!
納車は夕方の6時、その前にスペイン語の授業だった。
Kzさんは仕事で沖縄。
教室に入ると、スクリーンに "Feliz Cumpleaños" (Happy Birthdayの意)と大きな文字で映し出されている。
前のクラスの誰かの誕生日だったに違いない・・・自分をお祝いしてもらっているみたいないい気分。
パトリシア先生に「誰か誕生日だったのですか?」とお聞きすると
「セニョール・タカハシが80歳の誕生日だったのよ、あのお元気さで80歳!」
(タカハシさんはとても素敵な紳士、冬のクラスでご一緒したけれど温かくて控えめでいつも笑顔の絶えない本当に素敵なおじさまなのだ。)
「わあ、すごい、そうだったのですね。 ところで今日、私も誕生日なのです」とつい言ってしまったら、先生眼を輝かせて・・・
「でも、私は80歳じゃありませんから」と言うと、ニッコリして、
「No, Señora Sora」素敵な笑顔。
「un momentito (ちょっと待ってください)」と教室を出て行かれた。
メキシコの誕生日のお祝いのときの歌をプリントしてもらいに行ってくださったのだ。
授業の途中で、すごい嵐になり、雷に雹に強風に・・・みんなで窓を開けて眺めてしまった。教室内で良かった!
雨女の私も最近雨に遭わない。雨でも嵐でも、危機一髪!家に入った瞬間に始まるから、少し運が向いて来たのかもしれない。(今までは、外に出れば快晴でも雨が降ってきたものだ)
まるで悪夢のようだったここ数年の厄払いみたいに、スッキリ!デビルの灰を洗い流されたような気がする。
最後には "Las Mañanitas" という、メキシコの誕生日に歌う伝統的な歌をクラスのみんなと一緒に歌って下さった。平和な明るい曲。先生の声はとてもきれい。
みんなの声は温かい・・・こうして、幸せな61歳がスタートした。
帰宅後、偶然急いで買うことになった初対面の我が車はとても素敵で、仲良くなれそうだった。何しろまだパンフレットもできてないのだから。どんな車がやって来るのかドキドキだった。
営業担当のMさんは、「誕生日の納車って、ほとんどないのですよ。とても珍しいのです」と芍薬とバラとトルコ桔梗のとても私的色合いの素敵な花束を下さった。
女性にはいつも花束は幸せを運んでくれる。私はとても幸せで芍薬のようはポッペになったのではないだろうか?
思いがけないことばかりの上、自分がレディになった気分で、素敵な誕生日だった。(そういえば去年はガツガツ食べてお腹を壊して、上に下に一晩中苦しんだのだった。嫌なものを全部出してしまった意味合いにおいては、ゼロからのスタートだったが、今年はスタート時点で二年前より上向きだ)
さあ、車は4WDのターボ、山道用だ。
おてんばな私はさりげなく、格好良い中年になれるように
"ぶっ飛ばして、行ってみよう!!"
2012年5月27日日曜日
女性の年齢って・・・
我が家はバラの花が真っ盛り、素敵な季節を迎えています。
パンジーが終わって、クリスマスローズもくすんだ色になってきて、ジャーマンアイリスの季節が何となく過ぎ、裏のローズマリーが華やかになってきました。
ところで、最近女性の年齢が全く分からないことが多く、私の友人たちもそれぞれに大変なことを抱えているにも関わらず皆さんとてもおしゃれで美しく、全然変わらない。
50代から80代まで、何歳の人も活き活きと生きているせいか、普通の主婦なのにとても輝いています。
でも、テレビを観ていて気になっていたことがあったのですが・・・人に観られることが仕事の女優さんたちも、全然変わらない女優さんと、いやあ、老けたねえ〜と思う女優さんがあるのはどうしてなのかしら?その違いってなんなのだろう?と心に引っかかっていました。
黒木メイサと多部未華子主演の『ジウ』で、食堂のおばさん役の岸本加世子さんを観た時、あまり久しぶりだったせいか、役柄のせいか、二重あごのせいか、、、年月が経ったことを感じました。すっかりおばさんになっている。
だって、フジカラー♪♪のCMで樹木希林と出演していた時(多分もう30年くらい前のことだと思うけれど、「美しい人は美しく、そうでない人はそれなりに〜」ってすごく受けた)の彼女と樹木希林を比べると、希林さんは全然イメージが変わらない(始めから老けていた?)のに比べて、彼女は年月を感じた。とは言え、自然で決して悪い感じはしなかったのだが。(もっとも子供が30年過ぎれば30歳、それはもう別人だし、20歳の人が50になればそれは変わりますよね?だからその差は若い程激しいのでしょう)
又、先日テレビで久しぶりに女優の浅野ゆう子さんが出ている刑事物を観た時も、時々彼女は観ていたから今回は急な変化だったのか、「いやあ、女優さんでも老けちゃうんだ」ってびっくりした。
プロポーションが良かった彼女が、ちょっと精進を怠たったかな?と思わせるような感じで全体が幾分重くなっていて気になった。太ろうがなんだろうが全く構わないのだが、今の彼女そのものを使えばよいのに、昔のイメージにあてはめようとしているような感があり、少々無理を感じた。多分その人の年齢にしては素晴らしいのだが、世の中にはもう若い格好いい子たちがわんさといるので、年取ってプロポーションで競っても仕方ない。
八千草薫さん、野際陽子さん、市原悦子さん、黒柳徹子さん、若尾文子さん、岸恵子さん、樹木希林さんなどは年の取り方に不自然さがなく、私にとってはいつまでも若く美しく、本当に年齢を感じさせない素敵な女優さんたちだ。多分並々ならね努力をしておられるのだろうが、自分に合ったセンスの良さとプロの女優魂みたいなものを感じる。
美貌だけを売っているのではなく、その人自身から出て来るプラスαがある女優さんたちだ。
多分、吉永小百合さんや大竹しのぶさんや桃井かおりさん、竹下景子さん、余貴美子さん、原田美枝子さんなんかもその部類に入っていくのではないだろうか。
中谷美紀さんなども、女優魂を感じるから、年齢を重ねてそうあって欲しい。
異様に皺がなくて、お肌がつやつやで、痩せて贅肉がなく、いつも口角が上がり、目尻がたれ下がらないように色々努力するあまりむしろ引きつり・・・という見かけ重視のメンテをしている女優さんやタレントさんが最近多いが、どうもそういう人は私にはあまりきれいに見えない。
人のことを言うのは簡単だ。
だから勝手な言い草はこれくらいにして、明日61歳になる私も精進しよう。
周りの美しい人々からいっぱい元気をもらって、太っていたっていいし、若く見えなくてもいい、けれど、自分をしっかり持ったセンスの良い女性になりたいものだ。
女の真価はあらゆるものが内面から滲み出て来る還暦過ぎてからさ!
「美しい人は美しく、そうでない人もそれなりに・・・」
2012年5月23日水曜日
狭心症と老人介護と『背中で道徳的な人』
今日は久しぶりに朝から狭心症の発作を起こしてしまい、又ニトロのお世話になった。
昨年末に、冠動脈CTと心筋シンチグラフィの検査をした後、半年程快調で発作が全然起きなかったのに、何故か今日来てしまい、ニトロ服用後のだるさがおおっている。
この発作の後に母の所へ行くのは本当にきつい。
何故かと言うと心底明るくできなくて、寛容でなくなるので、いつも簡単に受け入れられることが、かなり無理をしないと受け入れられなくなるからだ。
私の受け答えが素っ気ないから、不満を感じて益々母が駄々っ子になる。
今日の私は頑張っても、駄々っ子の相手はできない。
私も再び心臓の血管が痙攣しそうな気分になる。
今日の毎日新聞にこんな記事があった:
『背中で道徳的な人』というタイトルで、鹿島茂さんの記事だ。
ジンメルという人の『愛の断想 日々の断想』という本からの引用らしいが
"或る道徳的な決意を試み、これを実現しようとする。ところが、それが、初め考えていたより大きな力や大きな犠牲を伴うことがある。しかし、私たちは、それに対してもう責任を負うことができない。"
そうすると、もはや欲するのではなく、ただそうせざるを得なくなるという段階に達する。
そこで、個々人の意志や努力ではどうにもならない巨大な問題を前にした時、人はどう対処すべきか? ジンメルは「軽薄さ」で対処しなさいと言ったらしい。
対立して調和し難い、衝動・義務・努力・憧憬に襲われ、更に突き詰めて自分が粉々にされてしまう前に、ふっとひと呼吸して「まっ、こんなもんでいいか」というある程度の軽薄さを持つことが大事だということらしい。
たまたま目にした記事を、そこから自分的に読ませていただき、今日の苦痛で粉々になる前に「まっ、いいか!」と・・・
えっ!? いつもかなりな程度の軽薄さですと??
昨年末に、冠動脈CTと心筋シンチグラフィの検査をした後、半年程快調で発作が全然起きなかったのに、何故か今日来てしまい、ニトロ服用後のだるさがおおっている。
この発作の後に母の所へ行くのは本当にきつい。
何故かと言うと心底明るくできなくて、寛容でなくなるので、いつも簡単に受け入れられることが、かなり無理をしないと受け入れられなくなるからだ。
「そんなことくらい、我慢してよ。」って言いたくなるけれど、そこからの跳ねっ返り係数の強さを思うと、とても太刀打ちできないので、それを言う気力も出ず言葉を飲み込んでしまう。
「今日は自分のことで精一杯、ここに来るのでやっとよ」と言いたいのだが、うだうだ説明できない。それが言えないのが体調の悪さを物語っている。窒息しそうなストレスだ。
さすが親子で、相手も感がよいので、私のイライラに反応するから余計やりにくい。
とても疲れた。
この疲れって、マジきつい。私の受け答えが素っ気ないから、不満を感じて益々母が駄々っ子になる。
今日の私は頑張っても、駄々っ子の相手はできない。
私も再び心臓の血管が痙攣しそうな気分になる。
今日の毎日新聞にこんな記事があった:
『背中で道徳的な人』というタイトルで、鹿島茂さんの記事だ。
ジンメルという人の『愛の断想 日々の断想』という本からの引用らしいが
"或る道徳的な決意を試み、これを実現しようとする。ところが、それが、初め考えていたより大きな力や大きな犠牲を伴うことがある。しかし、私たちは、それに対してもう責任を負うことができない。"
そうすると、もはや欲するのではなく、ただそうせざるを得なくなるという段階に達する。
そこで、個々人の意志や努力ではどうにもならない巨大な問題を前にした時、人はどう対処すべきか? ジンメルは「軽薄さ」で対処しなさいと言ったらしい。
対立して調和し難い、衝動・義務・努力・憧憬に襲われ、更に突き詰めて自分が粉々にされてしまう前に、ふっとひと呼吸して「まっ、こんなもんでいいか」というある程度の軽薄さを持つことが大事だということらしい。
たまたま目にした記事を、そこから自分的に読ませていただき、今日の苦痛で粉々になる前に「まっ、いいか!」と・・・
えっ!? いつもかなりな程度の軽薄さですと??
2012年5月20日日曜日
"Los fugitivos" 〜逃亡者たち〜
私たちのスペイン語の仲間では、年二回のペースで学校がオフの時にスペイン語の原書を読んでみんなで意見を交換している。
今使っているのは:Antología "Los mejores relatos latinoamericanos" というラテンアメリカの傑作短編集。
この会は、最初3年がかりで、マリオ・ベネデッティの"La tregua"を翻訳したところからスタートしたのだが、私たちの実力で難解なスペイン語の小説を正確に訳すのはあまりの骨折りで、それが終わった段階からは「もっと楽しんで短編を気楽に読みながら〜」という方針に変わった。
それでも、これはとても楽しい作業で、準備は大変だが、原書を読みながらパトリシア先生を囲んでみんなで意見交換をできるのはとても素敵だ。もちろんその意見交換はスペイン語で行われるので、うまく表現できず、思ったことの半分も伝えられないので少々消化不良ぎみでもあるのだが・・・楽しくてそんなことはどうでも良くなるから不思議だ。
今回の作品 "Los fugitivos" は、アレホ・カルペンティエル(Alejo Carpentier)というスイス、ローザンヌ生まれのキューバのジャーナリストである小説家の短編である。
後になって知ったが、日本では1978年に蔵原惟人によって『犬と逃亡奴隷』というタイトルで短編名作集の中で訳されているらしい。
ハイチ革命というハイチの黒人奴隷の反乱につながる世界を描いているのだと思うが、サトウキビ工場から逃亡した黒人奴隷と、逃亡者を追跡する立場にある番犬で、群れから離れてしまった名前を持たない『犬』の二人(?)の逃亡者を対比しながらメタファーを使って皮肉に力強くえぐるように心理をついて描いている作品だ。
この日は、大嵐が来る日で、時間がたっぷりなかったので、後で先生にメールで言い足りなかったことを送った。それを載せておく。
犬はそれほど服従を嫌い、鞭を嫌い、、、初めは一人になって恐くて寂しくて遠くの野犬の鳴き声にすらびくびくしていたが、夜の闇から始まって、色々な命がけの戦いを勝ち抜く毎に、野生化しながら強くなり仕舞いには一時は友だちだった再び逃亡して来た黒人奴隷すらも引きちぎって食べてしまう。こうして勝ち得た生き延びるための自由。
(ここで勝ち得た自由はハイチの革命で勝ち得た自由と比較したらどうなのだろうか?)
しかし、そこで得た本当の自由は、永遠の戦いの繰り返しがないと得られない物であり、ある時は以前友人だったものでも敵になり殺さないと得られない物であるという、どうしようもない不条理さが隠されている。
それでも、奴隷で屈するよりそのいばらの道を選ぶ・・・という疑問の投げかけは、私たちへの問いかけとなる。
ラテンアメリカの文学はすごい。
ちなみに、第一回目はガルシア・マルケスの"En este pueblo no hay ladrones" (この町に泥棒はいない)でした。
今使っているのは:Antología "Los mejores relatos latinoamericanos" というラテンアメリカの傑作短編集。
この会は、最初3年がかりで、マリオ・ベネデッティの"La tregua"を翻訳したところからスタートしたのだが、私たちの実力で難解なスペイン語の小説を正確に訳すのはあまりの骨折りで、それが終わった段階からは「もっと楽しんで短編を気楽に読みながら〜」という方針に変わった。
それでも、これはとても楽しい作業で、準備は大変だが、原書を読みながらパトリシア先生を囲んでみんなで意見交換をできるのはとても素敵だ。もちろんその意見交換はスペイン語で行われるので、うまく表現できず、思ったことの半分も伝えられないので少々消化不良ぎみでもあるのだが・・・楽しくてそんなことはどうでも良くなるから不思議だ。
今回の作品 "Los fugitivos" は、アレホ・カルペンティエル(Alejo Carpentier)というスイス、ローザンヌ生まれのキューバのジャーナリストである小説家の短編である。
後になって知ったが、日本では1978年に蔵原惟人によって『犬と逃亡奴隷』というタイトルで短編名作集の中で訳されているらしい。
ハイチ革命というハイチの黒人奴隷の反乱につながる世界を描いているのだと思うが、サトウキビ工場から逃亡した黒人奴隷と、逃亡者を追跡する立場にある番犬で、群れから離れてしまった名前を持たない『犬』の二人(?)の逃亡者を対比しながらメタファーを使って皮肉に力強くえぐるように心理をついて描いている作品だ。
この日は、大嵐が来る日で、時間がたっぷりなかったので、後で先生にメールで言い足りなかったことを送った。それを載せておく。
つまり、この作品はある意味では、『犬』の自立の物語であり、犬は犬なのだが、黒人に対して何か別の生き方をした人間の化身を犬として描き、比喩を使って、孤独に負けて怠惰に屈し死に行く黒人奴隷に対し、あらゆる戦い(監督:奴隷、一匹狼:群れ、白人:黒人、犬:奴隷、権力:服従、自由:空腹、自由:孤独・恐怖、強者:弱者、依存:独立・・・)に打ち勝った『犬』が本当の自由を勝ち得て生き延びた。A causa del tiempo mal, no teníamos horas suficiente.
Tenía más cosas deseaba decir como: "Es la historia de independencia de Perro."
"Hay muchas guerras para su independencia como :
Perros contra humano,
Perro contra jibaros,
blancos contra negro,
Perro contra Cimarron,
fugitivo contra policia,
autoridad contra obediencia,
libertad contra hambre,
libertad contra soledad,
los fuertes contra los débiles,
grupo contra solo (individual),
dependencia (pertenecer?) contra independencia,,,etc
En esta situación para hacerse independencia debe de luchar contra algo como la lista arriba.
Es Perro.
O si no es fuerte, solamente debe de morir como Cimarron.
犬はそれほど服従を嫌い、鞭を嫌い、、、初めは一人になって恐くて寂しくて遠くの野犬の鳴き声にすらびくびくしていたが、夜の闇から始まって、色々な命がけの戦いを勝ち抜く毎に、野生化しながら強くなり仕舞いには一時は友だちだった再び逃亡して来た黒人奴隷すらも引きちぎって食べてしまう。こうして勝ち得た生き延びるための自由。
(ここで勝ち得た自由はハイチの革命で勝ち得た自由と比較したらどうなのだろうか?)
しかし、そこで得た本当の自由は、永遠の戦いの繰り返しがないと得られない物であり、ある時は以前友人だったものでも敵になり殺さないと得られない物であるという、どうしようもない不条理さが隠されている。
それでも、奴隷で屈するよりそのいばらの道を選ぶ・・・という疑問の投げかけは、私たちへの問いかけとなる。
ラテンアメリカの文学はすごい。
ちなみに、第一回目はガルシア・マルケスの"En este pueblo no hay ladrones" (この町に泥棒はいない)でした。
2012年5月18日金曜日
弱音を吐こう介護日誌(27)〜エッ!パンツ5枚もはいてるの??
最近オババが少し太り始めたような気がしていた。
特に腰回りが・・・
心配で看護婦さんの高尾さんに
「太ったよう気がするのですが・・・」と相談したら、
「そうですか?体重は変わりませんよ」と言われたばかりだった。
腕が痛いので服用中のリリカカプセルの副作用ではないかと心配していたのだが・・・
何と、昨日私が帰る直前にトイレに行ってドアを開けたまま、
「トイレに行ってもいいけど、ズボン上げるのに時間かかって・・・面倒ねえ」
とぶつぶつ言いながらパンツを上げている。
ふと見ると、確かに窮屈そうだ。
「ちょ、ちょっと待ってお母さん、いったい何枚はいてるの?」
「冷えるからねえ〜」(--おいおい、今何月だ?)
「一枚、に〜まい、さんまい・・・」(番町皿屋敷じゃないんだよ)
「まだまるまって一枚残っているよ」
すったもんだの末、最後にウエストゴムのLLサイズのズボンをあげてだるまさんのようになって終わり!見事にブサイクだ。
ズボンを入れて6枚、はいていた!!
ショーツ2枚、三分丈一枚、五分丈とひざ下のズボン下の計5枚のパンツだ。
おまけに、靴下の下に、ハイソックスまではいて、シャツの上からブラジャーをつけて、この部屋は西日が入って暑い暑い、嫌な部屋ねえ〜と文句タラタラ・・・
メチャクチャだ。
確か、足がだるいだるいと言うので、「あまり締め付けると足が浮腫むよ、血行良くしておいてあげないとね。」と言って、冬の間に下着3枚で納得させたところだったのに、油断した。
脱いでも寒くなく、軽くなるだけでかえって具合が良いと喜んでいたのだが。
いつ戻ってしまったの?
そういえば以前もこんなことがあったなあ〜?何だったか忘れたけれど。
そうそう、もうほころびて汚いので捨てた下着が又タンスの中に。
捨てたはずのご汚いスリッパが、何度捨てても部屋の隅に。何度殺しても生き返ってくるホラームーヴィのようだ。呪いのスリッパ!
多分あの部屋は時計が逆回りするのだろう?
オババも若返るかもしれない。
油断めさるナ、ソラさん!
特に腰回りが・・・
心配で看護婦さんの高尾さんに
「太ったよう気がするのですが・・・」と相談したら、
「そうですか?体重は変わりませんよ」と言われたばかりだった。
腕が痛いので服用中のリリカカプセルの副作用ではないかと心配していたのだが・・・
何と、昨日私が帰る直前にトイレに行ってドアを開けたまま、
「トイレに行ってもいいけど、ズボン上げるのに時間かかって・・・面倒ねえ」
とぶつぶつ言いながらパンツを上げている。
ふと見ると、確かに窮屈そうだ。
「ちょ、ちょっと待ってお母さん、いったい何枚はいてるの?」
「冷えるからねえ〜」(--おいおい、今何月だ?)
「一枚、に〜まい、さんまい・・・」(番町皿屋敷じゃないんだよ)
「まだまるまって一枚残っているよ」
すったもんだの末、最後にウエストゴムのLLサイズのズボンをあげてだるまさんのようになって終わり!見事にブサイクだ。
ズボンを入れて6枚、はいていた!!
ショーツ2枚、三分丈一枚、五分丈とひざ下のズボン下の計5枚のパンツだ。
おまけに、靴下の下に、ハイソックスまではいて、シャツの上からブラジャーをつけて、この部屋は西日が入って暑い暑い、嫌な部屋ねえ〜と文句タラタラ・・・
メチャクチャだ。
確か、足がだるいだるいと言うので、「あまり締め付けると足が浮腫むよ、血行良くしておいてあげないとね。」と言って、冬の間に下着3枚で納得させたところだったのに、油断した。
脱いでも寒くなく、軽くなるだけでかえって具合が良いと喜んでいたのだが。
いつ戻ってしまったの?
そういえば以前もこんなことがあったなあ〜?何だったか忘れたけれど。
そうそう、もうほころびて汚いので捨てた下着が又タンスの中に。
捨てたはずのご汚いスリッパが、何度捨てても部屋の隅に。何度殺しても生き返ってくるホラームーヴィのようだ。呪いのスリッパ!
多分あの部屋は時計が逆回りするのだろう?
オババも若返るかもしれない。
油断めさるナ、ソラさん!
2012年5月17日木曜日
似ている!『セント・オブ・ウーマン』と『ムーン・パレス』
以前から気になって仕方なかったことがある。
アル・パチーノ主演の映画『セント・オブ・ウーマン』とポール・オースターの小説『ムーン・パレス』が「似ている!」と感じて私の頭の中でリンクしてしまい困っていたことだ。
文学好きや映画好きに、「似ていませんか?」って聞いても、怪訝そうな顔をするだけでなかなか同意してくれる人はいない。そんなに突拍子な発想だろうか?
今回久しぶりに両者を観て、読んで「ああ、そうか!これに反応していたのか?」と、気持ちがスッキリした。
映画のアル・パチーノの演技は素晴らしく、盲目の彼が狂気じみた会話の台詞の途中で時々発する「ハッ!」といううなり声ともため息ともつかない奇声が、ムーンパレスのジュリアン・バーバこと、トマス・エフィング老人の会話中に挟む「ハッ!」という音と共鳴してしまっていたのだった。
もちろんそれだけではない。
両者とも盲人で、稀にみる頑固者、さらに孤独の典型のような孤独な生活で・・・
アルは元軍人で、杖を使えば歩けるから障害物の位置さえ把握できればタンゴまで踊ってしまうけれど、画家であったエフィングに至っては、両足が死んでしまっているから車椅子以外に移動手段はない。しかも両者とも死のうと思っていることに変わりがない。
そんな状態の彼らを、苦学生のチャーリーが、散々もがき苦しんだ学生の成れの果てのマーコ・フォッグが手となり足となり世話をするはめに・・・
しかも、ふたりともとても献身的で、その誠実な姿が重なってしまう。
ムーンの方は長い小説なので、老人との関わり箇所は一部であり、セントではそれが全てであるが、その部分の印象の強さでは、二つが重なってしまっても仕方ないと思った。
ムーン・パレスが映画化されたら、アル・パチーノが老人の役をやれば多分みんな私の言っている意味を分かってくれるとおもうのだ。
ムーン・パレスは訳者の柴田さんのお話では、ポール・オースターが「私がいままで書いた唯一のコメディ」と言っているらしいが、「う〜〜ん!ホント?」と聞き返したくなる。
が、描写の可笑しさは確かにコメディ調だし、よく考えると登場人物や彼らがやっていることはメチャクチャだ。こんな極限あるのか??と思えるくらい滅茶苦茶なのに、作品を通して夢中になっていると、全然不自然ではなく、引き込まれてしまう。
作家本人にコメディと言われると、もっと力を抜いて楽しんで読まないといけないかな?なんて急に自由な気分になり、するとふわ〜〜と作品広がって又違った味が出て来るから不思議だ。映画好きはその世界の転換が実に柔軟だ。
もっとも自分が単純なだけかもしれないが・・・。
そんな訳で、今回は謎が解けてホッとした。
しかし親子三代に渡る因縁の連鎖は実に面白い。
妻を捨てて、捨てた妻が妊娠していて子供ができていたことすら知らなかったおじいさん、その息子が父を知らず、先生をしていた時に、女子学生と一回だけ結ばれて、他人になさぬ仲を目撃されてしまったために失踪してしまった彼女が、やはり妊娠していて生まれたのがマーコ。彼も父親のことは何も知らない。
そのマーコはというと、恋人のキティが妊娠して、どうしても産ませたかったのにキティはまだやりたいことがたくさんあるから、と産むことを拒絶し、マーコは自分の子と彼女を失うことになる。
しかし、大切なことは、バーバ家の呪われたような父と子のリンケージがここで途切れることではないかと思うのだ。(マーコはこの時点では少なくても父親の居ない、父親も子供が存在していることを知らない家族を残す可能性はないので)車とお金を盗まれ、おじいさんの洞窟は湖の下、父親も死んだし、キティも去った。
全てを失ったマーコはある意味では、過去から解放され、全くのゼロからの出発ができる状態になる。
何もないって、一番の自由なのかも、だって新しく生まれ変われるってことだから。
ここで、ムーンパレスで食べたフォーチュンクッキーに入っていた、この意味がよく分かるような気がする。
「太陽は過去であり、地球は現在であり、月は未来である」
アル・パチーノ主演の映画『セント・オブ・ウーマン』とポール・オースターの小説『ムーン・パレス』が「似ている!」と感じて私の頭の中でリンクしてしまい困っていたことだ。
文学好きや映画好きに、「似ていませんか?」って聞いても、怪訝そうな顔をするだけでなかなか同意してくれる人はいない。そんなに突拍子な発想だろうか?
今回久しぶりに両者を観て、読んで「ああ、そうか!これに反応していたのか?」と、気持ちがスッキリした。
映画のアル・パチーノの演技は素晴らしく、盲目の彼が狂気じみた会話の台詞の途中で時々発する「ハッ!」といううなり声ともため息ともつかない奇声が、ムーンパレスのジュリアン・バーバこと、トマス・エフィング老人の会話中に挟む「ハッ!」という音と共鳴してしまっていたのだった。
もちろんそれだけではない。
両者とも盲人で、稀にみる頑固者、さらに孤独の典型のような孤独な生活で・・・
アルは元軍人で、杖を使えば歩けるから障害物の位置さえ把握できればタンゴまで踊ってしまうけれど、画家であったエフィングに至っては、両足が死んでしまっているから車椅子以外に移動手段はない。しかも両者とも死のうと思っていることに変わりがない。
そんな状態の彼らを、苦学生のチャーリーが、散々もがき苦しんだ学生の成れの果てのマーコ・フォッグが手となり足となり世話をするはめに・・・
しかも、ふたりともとても献身的で、その誠実な姿が重なってしまう。
ムーンの方は長い小説なので、老人との関わり箇所は一部であり、セントではそれが全てであるが、その部分の印象の強さでは、二つが重なってしまっても仕方ないと思った。
ムーン・パレスが映画化されたら、アル・パチーノが老人の役をやれば多分みんな私の言っている意味を分かってくれるとおもうのだ。
ムーン・パレスは訳者の柴田さんのお話では、ポール・オースターが「私がいままで書いた唯一のコメディ」と言っているらしいが、「う〜〜ん!ホント?」と聞き返したくなる。
が、描写の可笑しさは確かにコメディ調だし、よく考えると登場人物や彼らがやっていることはメチャクチャだ。こんな極限あるのか??と思えるくらい滅茶苦茶なのに、作品を通して夢中になっていると、全然不自然ではなく、引き込まれてしまう。
作家本人にコメディと言われると、もっと力を抜いて楽しんで読まないといけないかな?なんて急に自由な気分になり、するとふわ〜〜と作品広がって又違った味が出て来るから不思議だ。映画好きはその世界の転換が実に柔軟だ。
もっとも自分が単純なだけかもしれないが・・・。
そんな訳で、今回は謎が解けてホッとした。
しかし親子三代に渡る因縁の連鎖は実に面白い。
妻を捨てて、捨てた妻が妊娠していて子供ができていたことすら知らなかったおじいさん、その息子が父を知らず、先生をしていた時に、女子学生と一回だけ結ばれて、他人になさぬ仲を目撃されてしまったために失踪してしまった彼女が、やはり妊娠していて生まれたのがマーコ。彼も父親のことは何も知らない。
そのマーコはというと、恋人のキティが妊娠して、どうしても産ませたかったのにキティはまだやりたいことがたくさんあるから、と産むことを拒絶し、マーコは自分の子と彼女を失うことになる。
しかし、大切なことは、バーバ家の呪われたような父と子のリンケージがここで途切れることではないかと思うのだ。(マーコはこの時点では少なくても父親の居ない、父親も子供が存在していることを知らない家族を残す可能性はないので)車とお金を盗まれ、おじいさんの洞窟は湖の下、父親も死んだし、キティも去った。
全てを失ったマーコはある意味では、過去から解放され、全くのゼロからの出発ができる状態になる。
何もないって、一番の自由なのかも、だって新しく生まれ変われるってことだから。
ここで、ムーンパレスで食べたフォーチュンクッキーに入っていた、この意味がよく分かるような気がする。
「太陽は過去であり、地球は現在であり、月は未来である」
【後日談】
数日後にふと思い出し、紅茶の"ムーンパレス"を飲みながら、このブログを読み直していた。ちょっとおしゃれな気分だった。
マリアージュ・フレールの店長さんとも話したが、「今読んでいる本と同じ名前なのですよ」と滅多に手に入らないお茶を買ってきたが、なかなか味わい深い。ちょっぴりチャイナの香りがして、やはりあの世界の香りがする。
2012年5月15日火曜日
『身体の言い分』 内田樹 池上六朗
このお二人の対談集を読んでいると、何だか妙にリラックスして、細かいことはどうでもいいような気になって来ます。
でも、お二人ともに『いやなものだけやめたら、チャンスは向こうからやって来るから・・・』とおっしゃるが、余程長いスパンでものを考えられる人でないと、やってくるまで待てなくて、普通の凡人にはそんなにうまくいかないのでは?と思ってしまう・・・だって、人生色々大変だもの。
ここのところ内田さんの本を読む機会がちょっと増えてしまったが、(健全なる肉体に狂気は宿る)、 家の中の本を手に取ると、どこにでもこの名前があるような気がする程、Kzさんがそろえていました。
Kzさんはレヴィナスなんかから入って行ったようですが、私は全く家の中のそこらへんの本を取っただけで・・・タイトルを見て、身体のことなどが書いてあるから読んだ、そしたら内田さんの本だったというだけだ。
この本は最近読んだ安保さんの本 にも通じるものがあって、私は『自分が気持ちよく生きて行くことが、よい空気を生み出し、回りも気持ちよい空気で包み、みんなが心地よくなり気持ち良く生きることができる。そして、この気持ち良く生きることが、個人差はあるだろうが、その人のレベルにちょうどよい健康状態でいられる』という感じでとらえたが・・・
内田さんが気に入っておられる中村天風氏の『七戒』:
怒るな、恐れるな、悲しむな、憎むな、妬むな、悪口を言うな(言われても言い返すな)、取り越し苦労をするな
これは、京都のどこかのお寺の入り口にあったあった十善戒というのにも共通しているし、
前述の安保さんのお考えにも共通した部分が随分あるので、人間の生きる基本姿勢なのだろう。
本当にこれさえ守れれば、気持ち良く生きて行けるのかもしれない。
"取り越し苦労"に関しては、『健全なる〜』を読んだ時にも共感し、私は実行しているが、Kzさんのまわりは取り越し苦労の堅牢な城壁に囲まれていて、強制的にせざるをえない状態で、お気の毒だ。
その中で、どのように"comodo"な空気を作っていくか・・・のんびり見守って行きましょう!
池上六朗さんは初めて知った方で、『三軸修正法』というものがどういうものなのかまだよく分かりませんが、興味深いです。"痛い"ということはとても大事なことで、身体の声を聞きなさい、そして無理に人工的に治そうとしないで、よくよく身体の声に耳を傾け、受け入れながらやっていきなさいと・・・
それから、ふっと思う瞬間を大事にしなさいと。それが前述のチャンスとも関係するもので、ふっとやって来る思いに身をゆだねることがチャンスとの出会いの時のようだ。その感度があるかないか?が大きな違いだろう。
この、ふっ、なのだが、私は結構そんな感じで生きて来た。
しかし、チャンスがこちらに向かってやってきたかはわからないが・・・
ふっと思い立って、早稲田で文学の勉強を始めた。
ふっと思い立って、上智で仏語をやり始め、ふっと思い立ってフランスへ一人旅をした。
これは人生の大きな転換点になった。
ふっと思い立って、スペイン語を始めた、青山先生のアメリカ短編の世界入った。
病気でいつ死ぬか分からないからとスペインへ短期留学に行かせてもらった。
人がしてくれるのを待っていられないから、全部一人でやった。
そして、ひとつふっと思ったことをやる度に、何か自分をがんじがらめにしていた、束縛のようなものが一枚一枚剥ぎ取られていくような気がした。それは意識だけかもしれないし、実際の行動から得られた解放感かもしれない。
みんなじっくり考えたことではなくて、ある日ふっと湧き出て来たものだった。
もしかしたら、そんなこんなでやってきたことが、何となく一つの道になってそのcaminoは死ぬ時になって、ああここに向かっていたの?なんて感じで、どこかに通じているかもしれない。
だから、これからもふっと思ったら動いてみよう。
ふっと思って離婚してしまったりして・・・??
まあ、この対談のお二人は「自分のために良いように全てを処理するといい、すると結果的にいい人でいられる。すると自然と自分も含めてみんなが気持ちよくいられる」とおっしゃるのだが・・・
でも、お二人ともに『いやなものだけやめたら、チャンスは向こうからやって来るから・・・』とおっしゃるが、余程長いスパンでものを考えられる人でないと、やってくるまで待てなくて、普通の凡人にはそんなにうまくいかないのでは?と思ってしまう・・・だって、人生色々大変だもの。
ここのところ内田さんの本を読む機会がちょっと増えてしまったが、(健全なる肉体に狂気は宿る)、 家の中の本を手に取ると、どこにでもこの名前があるような気がする程、Kzさんがそろえていました。
Kzさんはレヴィナスなんかから入って行ったようですが、私は全く家の中のそこらへんの本を取っただけで・・・タイトルを見て、身体のことなどが書いてあるから読んだ、そしたら内田さんの本だったというだけだ。
この本は最近読んだ安保さんの本 にも通じるものがあって、私は『自分が気持ちよく生きて行くことが、よい空気を生み出し、回りも気持ちよい空気で包み、みんなが心地よくなり気持ち良く生きることができる。そして、この気持ち良く生きることが、個人差はあるだろうが、その人のレベルにちょうどよい健康状態でいられる』という感じでとらえたが・・・
内田さんが気に入っておられる中村天風氏の『七戒』:
怒るな、恐れるな、悲しむな、憎むな、妬むな、悪口を言うな(言われても言い返すな)、取り越し苦労をするな
これは、京都のどこかのお寺の入り口にあったあった十善戒というのにも共通しているし、
前述の安保さんのお考えにも共通した部分が随分あるので、人間の生きる基本姿勢なのだろう。
本当にこれさえ守れれば、気持ち良く生きて行けるのかもしれない。
"取り越し苦労"に関しては、『健全なる〜』を読んだ時にも共感し、私は実行しているが、Kzさんのまわりは取り越し苦労の堅牢な城壁に囲まれていて、強制的にせざるをえない状態で、お気の毒だ。
その中で、どのように"comodo"な空気を作っていくか・・・のんびり見守って行きましょう!
池上六朗さんは初めて知った方で、『三軸修正法』というものがどういうものなのかまだよく分かりませんが、興味深いです。"痛い"ということはとても大事なことで、身体の声を聞きなさい、そして無理に人工的に治そうとしないで、よくよく身体の声に耳を傾け、受け入れながらやっていきなさいと・・・
それから、ふっと思う瞬間を大事にしなさいと。それが前述のチャンスとも関係するもので、ふっとやって来る思いに身をゆだねることがチャンスとの出会いの時のようだ。その感度があるかないか?が大きな違いだろう。
この、ふっ、なのだが、私は結構そんな感じで生きて来た。
しかし、チャンスがこちらに向かってやってきたかはわからないが・・・
ふっと思い立って、早稲田で文学の勉強を始めた。
ふっと思い立って、上智で仏語をやり始め、ふっと思い立ってフランスへ一人旅をした。
これは人生の大きな転換点になった。
ふっと思い立って、スペイン語を始めた、青山先生のアメリカ短編の世界入った。
病気でいつ死ぬか分からないからとスペインへ短期留学に行かせてもらった。
人がしてくれるのを待っていられないから、全部一人でやった。
そして、ひとつふっと思ったことをやる度に、何か自分をがんじがらめにしていた、束縛のようなものが一枚一枚剥ぎ取られていくような気がした。それは意識だけかもしれないし、実際の行動から得られた解放感かもしれない。
みんなじっくり考えたことではなくて、ある日ふっと湧き出て来たものだった。
もしかしたら、そんなこんなでやってきたことが、何となく一つの道になってそのcaminoは死ぬ時になって、ああここに向かっていたの?なんて感じで、どこかに通じているかもしれない。
だから、これからもふっと思ったら動いてみよう。
ふっと思って離婚してしまったりして・・・??
まあ、この対談のお二人は「自分のために良いように全てを処理するといい、すると結果的にいい人でいられる。すると自然と自分も含めてみんなが気持ちよくいられる」とおっしゃるのだが・・・
2012年5月14日月曜日
いつ見ても不愉快なこと
最近の電車の中では全然珍しくないことなのだが、車中で化粧をしている若い女を見ると、とても不愉快な嫌な気持ちになる。年寄りでそんなみっともないことをしている人は見たことないし、外国人でもみかけない。
日本女性も質が下がってしまったと哀れみすら感じる。
毎週月曜日の午後は早稲田に通っているが、時々対面の座席に化粧をばっちり最初から最後までやっている女に出くわす。朝間に合わなくて〜と言う感じで遠慮がちにやっているのではもちろんない、だって午後も3時近くなのだから。
堂々としていてまるで車両内が化粧室とでも思っているのでは?と疑いたくなるほど手慣れたもので、どうみても日課のうちに入っている感じの落着きようだ。
今日の女性は表情のないのっぺらぼうのブスっぽい人だった。それも着ているものから察するに、本人は自分を可愛いと勘違しているのだろうなあ?タイプのブス。
バカっぽい顔をしていたが、早稲田で降りたのであれでも早稲田の学生なのだろう。
すっかり顔が脳にインプットされてしまって、どこかで出会ったら「あらこの間ののっぺらぼう〜」と声をかけてしまいそうだ。
イメージを追い払おうにもなかなか消えてくれない。インク消しが欲しい。
以前スペイン語のロメロ先生が日本でビックリしたことの一つに和式のトイレと電車内での女性の化粧の話しをあげていたが、やはり外国人から見ても異様な光景で、ありえない、飽きれてものも言えないたぐいの行動のようだ。(前者に関しては、日本に到着した日、どうしても我慢できず慌ててトイレに入ったが、和式ばかり。どのようにやったらよいか想像もつかず、途方に暮れたらしい。彼女が想像した格好はお腹がはち切れそうなほど傑作な方法だった。いずれにせよ切羽詰まって入ったのだろうからお気の毒)
というわけで、おばさん根性丸出して、不愉快を書き留めておく。
「そんなの自分の勝手じゃん!」と言われればそれまでなのですが、書かずにはおられなかったんよ。
だって、日本の女性って外国で見ると慎ましくて控えめで仕草が美しいよ。
日本女性も質が下がってしまったと哀れみすら感じる。
毎週月曜日の午後は早稲田に通っているが、時々対面の座席に化粧をばっちり最初から最後までやっている女に出くわす。朝間に合わなくて〜と言う感じで遠慮がちにやっているのではもちろんない、だって午後も3時近くなのだから。
堂々としていてまるで車両内が化粧室とでも思っているのでは?と疑いたくなるほど手慣れたもので、どうみても日課のうちに入っている感じの落着きようだ。
今日の女性は表情のないのっぺらぼうのブスっぽい人だった。それも着ているものから察するに、本人は自分を可愛いと勘違しているのだろうなあ?タイプのブス。
バカっぽい顔をしていたが、早稲田で降りたのであれでも早稲田の学生なのだろう。
すっかり顔が脳にインプットされてしまって、どこかで出会ったら「あらこの間ののっぺらぼう〜」と声をかけてしまいそうだ。
イメージを追い払おうにもなかなか消えてくれない。インク消しが欲しい。
以前スペイン語のロメロ先生が日本でビックリしたことの一つに和式のトイレと電車内での女性の化粧の話しをあげていたが、やはり外国人から見ても異様な光景で、ありえない、飽きれてものも言えないたぐいの行動のようだ。(前者に関しては、日本に到着した日、どうしても我慢できず慌ててトイレに入ったが、和式ばかり。どのようにやったらよいか想像もつかず、途方に暮れたらしい。彼女が想像した格好はお腹がはち切れそうなほど傑作な方法だった。いずれにせよ切羽詰まって入ったのだろうからお気の毒)
というわけで、おばさん根性丸出して、不愉快を書き留めておく。
「そんなの自分の勝手じゃん!」と言われればそれまでなのですが、書かずにはおられなかったんよ。
だって、日本の女性って外国で見ると慎ましくて控えめで仕草が美しいよ。
2012年5月10日木曜日
最年長の友人、Anne-marie とSalamanca, Spain
2008年7月にスペイン、Salamancaへ留学した。私にとったら、大大冒険旅行だった!!
たった2週間の語学留学だったが、その後バスク地方へ一人旅して、Madridに留学中だった息子に会ってトレドに行き、帰って来た。ひと月足らずのスペインだった。
その頃の私は狭心症の発作と、脳動脈瘤でショックを受けていて大変体調も悪く、「このまま死んでしまうのではつまらないから、スペインに短期留学させて欲しい、何かがあってもマドリッドに息子がいるから、多分助けてもらえるから」と夫を説得して行かせてもらった。
私の最も解放された自由の時だった。
ガチガチにかたまった、鎧を剥ぐのがそれはそれは大変だった。
わたしにとったら革命だもの。
そしてその時から自分の中の何かが変わったような気がする。
幸い脳動脈瘤はまだ破裂しないで生きているし、元気に暮らしている。
サラマンカ大学の寮で過ごした間に友だちになったフランス人アンヌ・マリーがメールをくれた。そもそも、頻繁にきれいな風景や美術作品のスライドを送ってくれるのだが、本人のプライベートなメッセージはほとんどついてこない。先日久しぶりにまとめてお礼のメールをしたら、今日返事がきた。
実は今まで、何度か返事を書いたが、ここのところ返事がなかったので、もう個人的なメールを書けるような状態ではないのだと思っていた。コンタクトだけはとりたいから、スライドを送ってくるのだと・・・。
歩行困難にはなってきているが、元気そうだ。良かった!
彼女は当時78歳だったから、多分今は82歳くらいだろう。心臓が悪くて何か装置を持っていたから、あまり調子は良くないと思う。
毎年夏はサラマンカでスペイン語を勉強しながら私の居た寮で、2ヶ月ほど過ごしていた。
日本が好きで、いつも食事の時は同じテーブルでおしゃべりしながら、日本語とフランス語とスペイン語で話し、行き詰まると英語でコミュニケーションを取った。
色々なことをお話した。
彼女が居なかったら、初めてのスペインで、知らない人ばかりの中で、言葉も分からず、不安ながらも一人で何もかもやっていた私の留学は随分違うものになったと思う。彼女はお節介はいけないかな?どこまで踏み込んでいいのかしら?と、暗黙のうちに気遣いながら私の好みを控えめにチェックし、出過ぎないで程よく色々誘ってくれたし、困ったことがあると何でも相談できた。
私の最年長の大切な友人だ。
メールの最後には、「あなたのともだち、アンヌ−マリー」と素敵な字体で、日本語で書かれていた。
思わず、ホロリ・・・あたたか〜〜いい。
82歳のフランス人が日本語を混ぜたメールをくれたのだ。とてもソフトな響きで、彼女の声が聞こえて来たような気がした。パソコンを使うだけでもすごいと思うのだが、仏語、英語、スペイン語は当然ペラペラ、日本が好きで日本語を一生懸命勉強していた。
漢字も書く、覚えようとする、驚くべきフランス人女性!
メールを読んでいたら、サラマンカが戻って来た。あの不思議な時間が、私の宝物が。
あの時から、自分の足で歩けるようになったような気がするのだから。
そして、エネルギーが心地よく充電された。
ちょっと気持ちが沈んでいたけれど、スペインの空気を思い出して、さあ、元気を出そう!
たった2週間の語学留学だったが、その後バスク地方へ一人旅して、Madridに留学中だった息子に会ってトレドに行き、帰って来た。ひと月足らずのスペインだった。
その頃の私は狭心症の発作と、脳動脈瘤でショックを受けていて大変体調も悪く、「このまま死んでしまうのではつまらないから、スペインに短期留学させて欲しい、何かがあってもマドリッドに息子がいるから、多分助けてもらえるから」と夫を説得して行かせてもらった。
私の最も解放された自由の時だった。
ガチガチにかたまった、鎧を剥ぐのがそれはそれは大変だった。
わたしにとったら革命だもの。
そしてその時から自分の中の何かが変わったような気がする。
幸い脳動脈瘤はまだ破裂しないで生きているし、元気に暮らしている。
サラマンカ大学の寮で過ごした間に友だちになったフランス人アンヌ・マリーがメールをくれた。そもそも、頻繁にきれいな風景や美術作品のスライドを送ってくれるのだが、本人のプライベートなメッセージはほとんどついてこない。先日久しぶりにまとめてお礼のメールをしたら、今日返事がきた。
実は今まで、何度か返事を書いたが、ここのところ返事がなかったので、もう個人的なメールを書けるような状態ではないのだと思っていた。コンタクトだけはとりたいから、スライドを送ってくるのだと・・・。
歩行困難にはなってきているが、元気そうだ。良かった!
彼女は当時78歳だったから、多分今は82歳くらいだろう。心臓が悪くて何か装置を持っていたから、あまり調子は良くないと思う。
毎年夏はサラマンカでスペイン語を勉強しながら私の居た寮で、2ヶ月ほど過ごしていた。
日本が好きで、いつも食事の時は同じテーブルでおしゃべりしながら、日本語とフランス語とスペイン語で話し、行き詰まると英語でコミュニケーションを取った。
色々なことをお話した。
彼女が居なかったら、初めてのスペインで、知らない人ばかりの中で、言葉も分からず、不安ながらも一人で何もかもやっていた私の留学は随分違うものになったと思う。彼女はお節介はいけないかな?どこまで踏み込んでいいのかしら?と、暗黙のうちに気遣いながら私の好みを控えめにチェックし、出過ぎないで程よく色々誘ってくれたし、困ったことがあると何でも相談できた。
私の最年長の大切な友人だ。
メールの最後には、「あなたのともだち、アンヌ−マリー」と素敵な字体で、日本語で書かれていた。
思わず、ホロリ・・・あたたか〜〜いい。
82歳のフランス人が日本語を混ぜたメールをくれたのだ。とてもソフトな響きで、彼女の声が聞こえて来たような気がした。パソコンを使うだけでもすごいと思うのだが、仏語、英語、スペイン語は当然ペラペラ、日本が好きで日本語を一生懸命勉強していた。
漢字も書く、覚えようとする、驚くべきフランス人女性!
メールを読んでいたら、サラマンカが戻って来た。あの不思議な時間が、私の宝物が。
あの時から、自分の足で歩けるようになったような気がするのだから。
そして、エネルギーが心地よく充電された。
ちょっと気持ちが沈んでいたけれど、スペインの空気を思い出して、さあ、元気を出そう!
2012年5月9日水曜日
『自分ですぐできる免疫革命』 〜安保徹〜
今年1月末に二度目の酵素温浴に行った後、Kzさんが買って来た本。
琉球温熱療法の施術師、Tさんお薦めの先生らしい。
前回の酵素風呂体験第一回目のブログは:酵素温浴と琉球温熱療法
忘れないうちにメモを残しておこう。
一見とても簡単そうな本なのだが、誰にでも分かるように書かれていて、とても信頼できる本だった。
以下は、読んだ直後のメモです。
著者は、安保 徹 (あぼ とおる) 新潟大学大学院教授
琉球温熱療法の施術師、Tさんお薦めの先生らしい。
前回の酵素風呂体験第一回目のブログは:酵素温浴と琉球温熱療法
忘れないうちにメモを残しておこう。
一見とても簡単そうな本なのだが、誰にでも分かるように書かれていて、とても信頼できる本だった。
以下は、読んだ直後のメモです。
著者は、安保 徹 (あぼ とおる) 新潟大学大学院教授
分かりやすい図解がついていて、しかし内容は正常でとても大事な事が書かれていてとても良い本でした。
時々引っ張りだして日常生活を再確認。
自分が日々忘れてはいけないこと、毎日意識したいことだけ、書いておこう。
1. 筋肉を使う ラジオ体操とウォーキングと柔軟体操
2. 深呼吸とリラックス
3. 良くかんで、バランスの良い食事を
4.入浴
5. 低体温を改善
6.副交感神経人間に
使ってはいけない薬 抗生物質 解熱剤 睡眠薬 消炎鎮痛剤
ストレス対策
1 働き過ぎない
2 悩み続けない
3 怒らない
4 頭より体を使う
5 バランスの取れた食事
6 睡眠時間の確保
7 良い人間関係
8 趣味を持つ
9 よく笑う
10 自然や芸術に触れる
穏やかな気持ちで感謝の念を忘れないこと
これができていれば、大病持ちでない限り、気持ち良く生きることができるばず。
さあ、免疫力を高めよう!!
2012年5月8日火曜日
認知症を恐がらずに暮らしていけるって・・・
6月号のクーリエにこんな記事が出ていた。
地域全体が介護ホーム オランダの幸せな"認知症村"
私はまだオランダには行ったことがない。
娘が仕事上の取引で何度か行ったと聞いて行ってみたいと思っていたが、まだ実現していない。
オランダと言えば風車と花と麻薬が合法だということくらいしか知らない。
行ったことのある友人が「あっちこっち、ヌードだらけよ〜」と言っていたが・・・
ところで、この記事はとても素敵だ。
アムステルダム郊外にある介護施設「ホーゲヴェイ」という所で認知症の老人たちが暮らしているらしい。
ここの特徴は、スーパー、カフェ、美容室などがあり小さな村の形態をとっているそうだ。塀で囲まれてはいるが、老人たちは村の中をどこでも自由自在に歩き回れるらしい。ここのあり方は世界中から注目されているという。
現在の入居者は152人。自分のライフスタイルに合わせて、棟を選べる。
迷子になっても、介護者が家まで連れて行ってくれるし、財布を忘れても大丈夫、間違えて買って来ても快く戻してくれる。だってスーパーの店員さんも介護者なのだから。
第一線で働いていた人たちが多いらしいが、認知症になりかかっているけれど、全く自分でなにもできないわけではない人には理想的かもしれない。
食事を作ったり、自分で洗濯したり何でも受け入れてもらって、慣れ親しんだ村の中で自然に年老いながら暮らすことができる。みんな少なからず惚けているから、自分のことをさほど心配することなく、自然体で受け入れてもらえるということなのだろう。
ホームの中だけが行動範囲の暮らしとは全く異なる。
2009年オープンというから、まだまだ色々な問題が発生するかもしれないが、年老いても人間らしく暮らせるのは心底ありがたいことだ。
村全体が惚けちゃった自分みたいな人ばかりで、介護者に何気なく見守られながら、平和に暮らしていけるのだったら、とても素晴らしいことかもしれないと思った。
できれば、惚けないでやって行けたら素敵だけど・・・
少なくても村の中を自由に歩けるのは今の母の生活と比べると天と地との差程の違いがあると思う。歩けるうちは、歩きたいのが当たり前だから。
地域全体が介護ホーム オランダの幸せな"認知症村"
私はまだオランダには行ったことがない。
娘が仕事上の取引で何度か行ったと聞いて行ってみたいと思っていたが、まだ実現していない。
オランダと言えば風車と花と麻薬が合法だということくらいしか知らない。
行ったことのある友人が「あっちこっち、ヌードだらけよ〜」と言っていたが・・・
ところで、この記事はとても素敵だ。
アムステルダム郊外にある介護施設「ホーゲヴェイ」という所で認知症の老人たちが暮らしているらしい。
ここの特徴は、スーパー、カフェ、美容室などがあり小さな村の形態をとっているそうだ。塀で囲まれてはいるが、老人たちは村の中をどこでも自由自在に歩き回れるらしい。ここのあり方は世界中から注目されているという。
現在の入居者は152人。自分のライフスタイルに合わせて、棟を選べる。
迷子になっても、介護者が家まで連れて行ってくれるし、財布を忘れても大丈夫、間違えて買って来ても快く戻してくれる。だってスーパーの店員さんも介護者なのだから。
第一線で働いていた人たちが多いらしいが、認知症になりかかっているけれど、全く自分でなにもできないわけではない人には理想的かもしれない。
食事を作ったり、自分で洗濯したり何でも受け入れてもらって、慣れ親しんだ村の中で自然に年老いながら暮らすことができる。みんな少なからず惚けているから、自分のことをさほど心配することなく、自然体で受け入れてもらえるということなのだろう。
ホームの中だけが行動範囲の暮らしとは全く異なる。
2009年オープンというから、まだまだ色々な問題が発生するかもしれないが、年老いても人間らしく暮らせるのは心底ありがたいことだ。
村全体が惚けちゃった自分みたいな人ばかりで、介護者に何気なく見守られながら、平和に暮らしていけるのだったら、とても素晴らしいことかもしれないと思った。
できれば、惚けないでやって行けたら素敵だけど・・・
少なくても村の中を自由に歩けるのは今の母の生活と比べると天と地との差程の違いがあると思う。歩けるうちは、歩きたいのが当たり前だから。
2012年5月5日土曜日
『コレラの時代の愛』 〜El amor en los tiempos de cólera
"El amor en los tiempos de cólera"

スペイン語の冬講座でハビエル・バルデムをやったときにも出て来た作品だが、彼の年代に応じての変化は実に見事だ。変化自在の役者にはピッタリの役柄だったかもしれない。しかし、残念ながら英語だったので、授業ではあまり話題にはならなかった。
まだ、原作を読んでないので、映画とのずれがどんなか分からないが、51年もの間一途に一人の女性への愛を貫き通したフロレンティーノの姿には、何だか男のロマンのようなものを感じる。
しかしフェルミーナにふられてから、身を引いて表には現れなかったものの、一種ストーカー的行為を50年以上も続けていたのではないか?と言った犯罪めいた奇妙な感じを持つのは私だけだろうか?
もし、自分がじっと見守られ続けていることに気づいてしまったら30代、40代あたりでは嬉しいのか恐いのか考えてしまう。
ただし、彼はひたすら待って、表に現れず、紳士的に静かにフェルミーナを見守り続けたので、彼女にとっては事実ストーカー被害とは違う。疑いようのない純愛に包まれ、ただただ見守られて来たのだから。
夫が亡くなったからと、いきなり登場するフロレンティーノに戸惑う彼女だが、「私はずっとあなたを見て来た」という彼にとっては一生供に歩いてきたのであり、他には伴侶はいないのであり、やっと求め続けた愛が成就することになる。しかも彼女に相応しい立派な(?女性遍歴の数を考えると本当に立派か考えてしまうが、精神的には純愛そのものであることは認めよう)魅力的な男として・・・。
社会的立場を確立しながらも、ひたすら彼女だけを思い続けるその姿は、"グレート・ギャツビー"を思わせる。
けれど、対象となる女性、フェルミーナのあり方は、ギャツビーのデイジーよりはずっと人間的で誇り高く、愛される女性像としては受け入れられる。
しかも悲劇ではなく、しっかりとしたたかに時間をたっぷりかけて(時間の観念が全く違うのが面白い、70歳を過ぎての巻き返しなのだから)思いを成し遂げているところが、南米らしくガルシア・マルケスらしく、生きる粘りとエネルギーがあっていい。
長編だが、いつか読んでみないといけないかな? いやいや、途中で沈没した"百年の孤独"が先だ。
2012年5月1日火曜日
『ヘルプ』 〜 The Help 〜
ひさしぶりに映画らしい映画を観た。
アメリカ映画はここのところ敬遠していたが、今日観た『ヘルプ』は素敵な作品だった。
『カラーパプル』や『ロングウォークホーム』『ドライビングミスデイジー』などと何かしら重なる雰囲気もあったが、その重さを痛快さに置き換えてくれて力強い気持ちのよい作品だった。
それが最初の『映画らしい映画』という表現になった。
私は青山南先生の影響でアメリカ南部に縁があったが、たくさん読んで来た南部の短編や小説にも通じるものがあり、久しぶりに懐かしささえ感じた。
公民権運動やKKKのことなど、色々勉強したが、こうして映画で観ると私の単純な頭でも印象に刻まれる。
主人公のスキーターを演じたエマ・ストーンはとても新鮮でうわついた軽薄さがなくて、この役にピッタリだった。
でも何と言っても印象的だったのは、シーリアを演じた、ジェシカ・チャスティン。今回の掘り出し物だ。
何ともおつむが少しいかれているの?って思わせるような意外な人物なのだが、その憎めない底抜けなチャーミングさがたまらない。
人格者なのか?と錯覚をおこしてしまうほどのこの人の演技力、、、光っていた。
焦点のずれた純粋さが人々の心に嫌みなく染み通って行く。
もう一つ、シシー・スペイセクの惚けたおばあちゃんと、メアリー・スティーンバージェンの出版業界のやり手ミス・スタインはうまかった。この二人が居なかったら、作品の雰囲気が出ない。
こんなにも多数の個性豊かな人材をうまく使いこなした作品は見事だった!
もちろん、エイヴィリンのヴィオラ・デイビスの静かな品位のある奥深さは言うまでもない。
そして、最後が単なるハッピーエンドではなく、職を失ったエヴィリンにはまだまだ先行き命がけの戦いが残されている。彼女は生きていかねばならないのだから・・。
そしてそれを暗示するような、長い長い南部独特の美しい豪邸にはさまれた街路樹をひたすら歩く彼女の後姿が心に残る。
いつまでも見守って応援していたい気持ちにさせるシーンだった。
それにしても、相変わらず駄目やなあ〜・・・南部男は。
登録:
投稿 (Atom)







